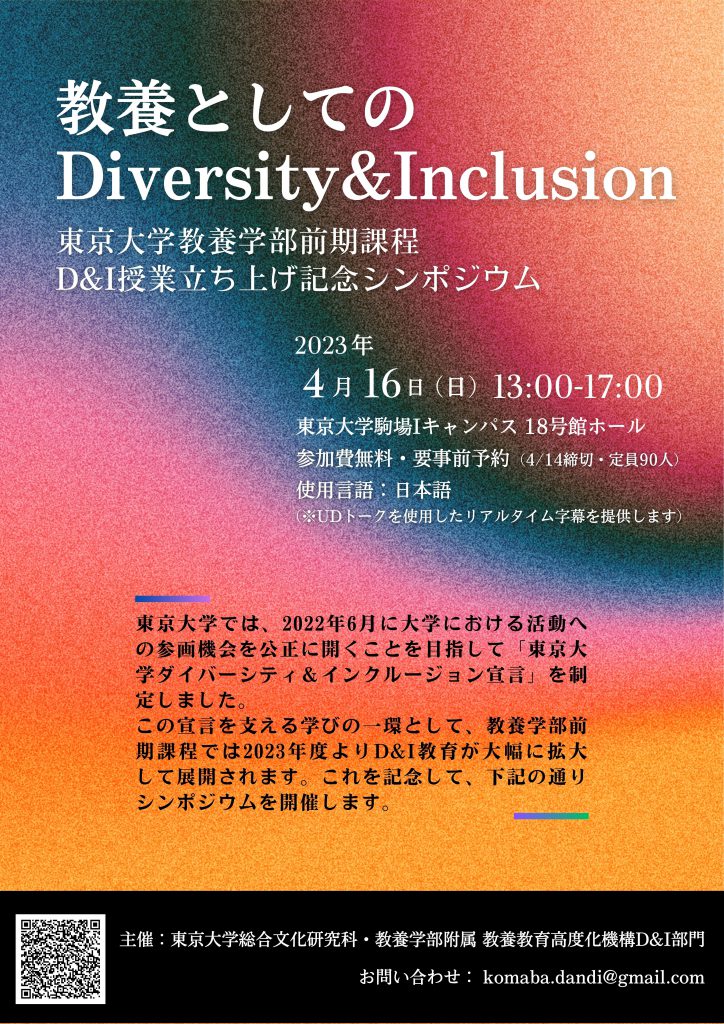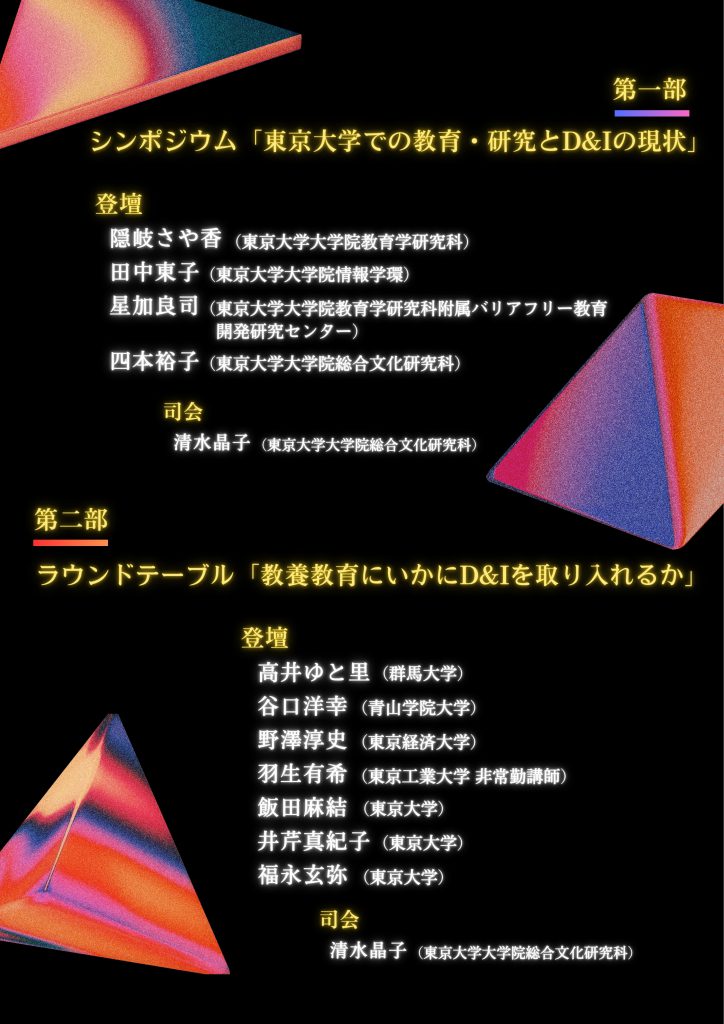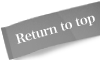日時:2023年3月13日(月)午後1時~5時
場所:東京大学駒場1キャンパス 18号館ホール
主催:東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構
企画:SDGs教育推進プラットフォーム
概要:2023年は、国連総会で合意したSDGsの折り返し点にあたる。しかし、新型コロナウイルス感染症パンデミック、頻発化・激甚化する自然災害、世界各地の紛争、史上初めて1億人を超えた難民・避難民問題、エネルギー・食料危機などが、その達成を阻んでいる。今、国、分野、世代を超えてSDGsに取り組むために何が必要なのか。本シンポジウムでは、「我々の世界を変革する」ために作られたSDGs達成に向けて鍵となる諸分野の第一人者をお迎えし、学問の垣根を越えて俯瞰すると共に、アクションについて議論し、ポスト2030に向けた未来を展望する。
プログラム(敬称略):
13:00 開会挨拶 真船文隆 東京大学大学院総合文化研究科副研究科長
機構の取組み 網野徹哉 東京大学教養教育高度化機構長
基調講演 石井菜穂子 東京大学理事・東京大学CGCダイレクター
13:15 第1部 講演「SDGsの現在地」
国連から見たSDGsの今 井筒節 東京大学大学院総合文化研究科特任准教授(国際連携部門)
開発途上国の現場におけるSDGsの現状 成田詠子 国連人口基金(UNFPA)駐日事務所長
開発経済学からみたSDGsの今 澤田康幸 東京大学大学院経済学研究科教授
気候変動による健康影響とSDGs 橋爪真弘 東京大学大学院医学系研究科教授
誰一人取り残さない社会 福島智 東京大学先端科学技術研究センター教授
15:00 学生団体紹介/各部門・学生団体紹介ポスター展示/休憩
Climate Youth Japan,UNiTeほか
15:30 第2部 パネル・ディスカッション「パートナーシップを通してSDGsのその先へ」
モデレーター:岡田晃枝 東京大学大学院総合文化研究科准教授(初年次教育部門)
パネリスト:
・ 榎原雅治 東京大学地震火山史料連携研究機構長・東京大学史料編纂所教授
・ キハラハント愛 東京大学大学院総合文化研究科教授
・ 白波瀬佐和子 国連大学上級副学長・東京大学大学院人文社会系研究科教授
・ 額賀美紗子 東京大学大学院教育学研究科教授
・ 瀬川浩司 東京大学大学院総合文化研究科教授(環境エネルギー科学特別部門長)
・ 原和之 東京大学大学院総合文化研究科教授(国際連携部門長)
17:00 閉会
閉会挨拶 廣野喜幸 東京大学大学院総合文化研究科教授(科学技術インタープリター養成部門長)
総合司会:松本真由美 東京大学大学院総合文化研究科客員准教授
お申し込み(参加費無料):
以下の参加登録フォームから、あらかじめご登録をお願い致します。
会場の定員に達し次第、参加登録を終了させて頂きます。
https://forms.gle/cJ2MnyGq1eGm3XE58